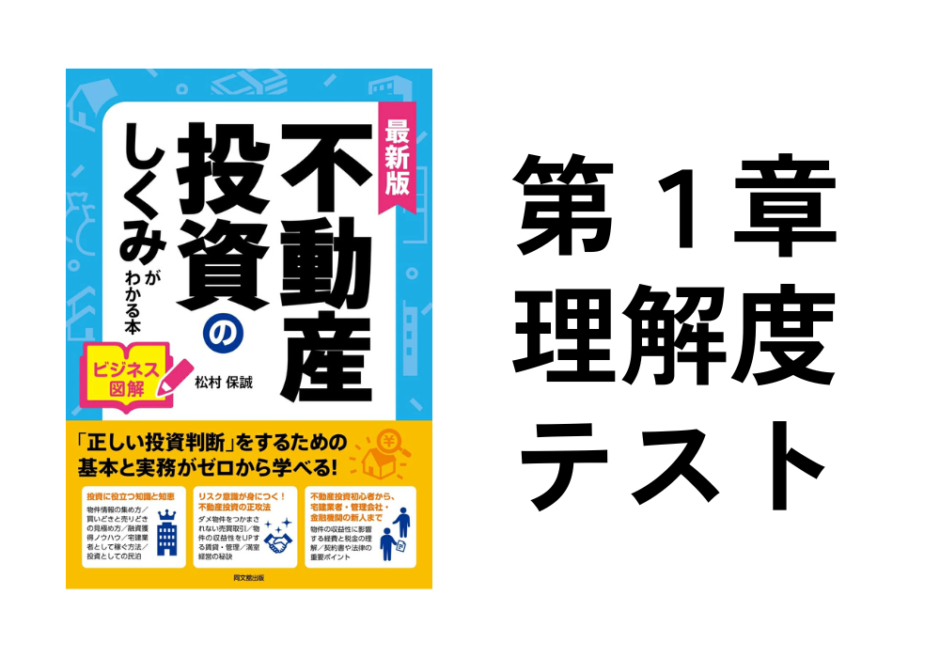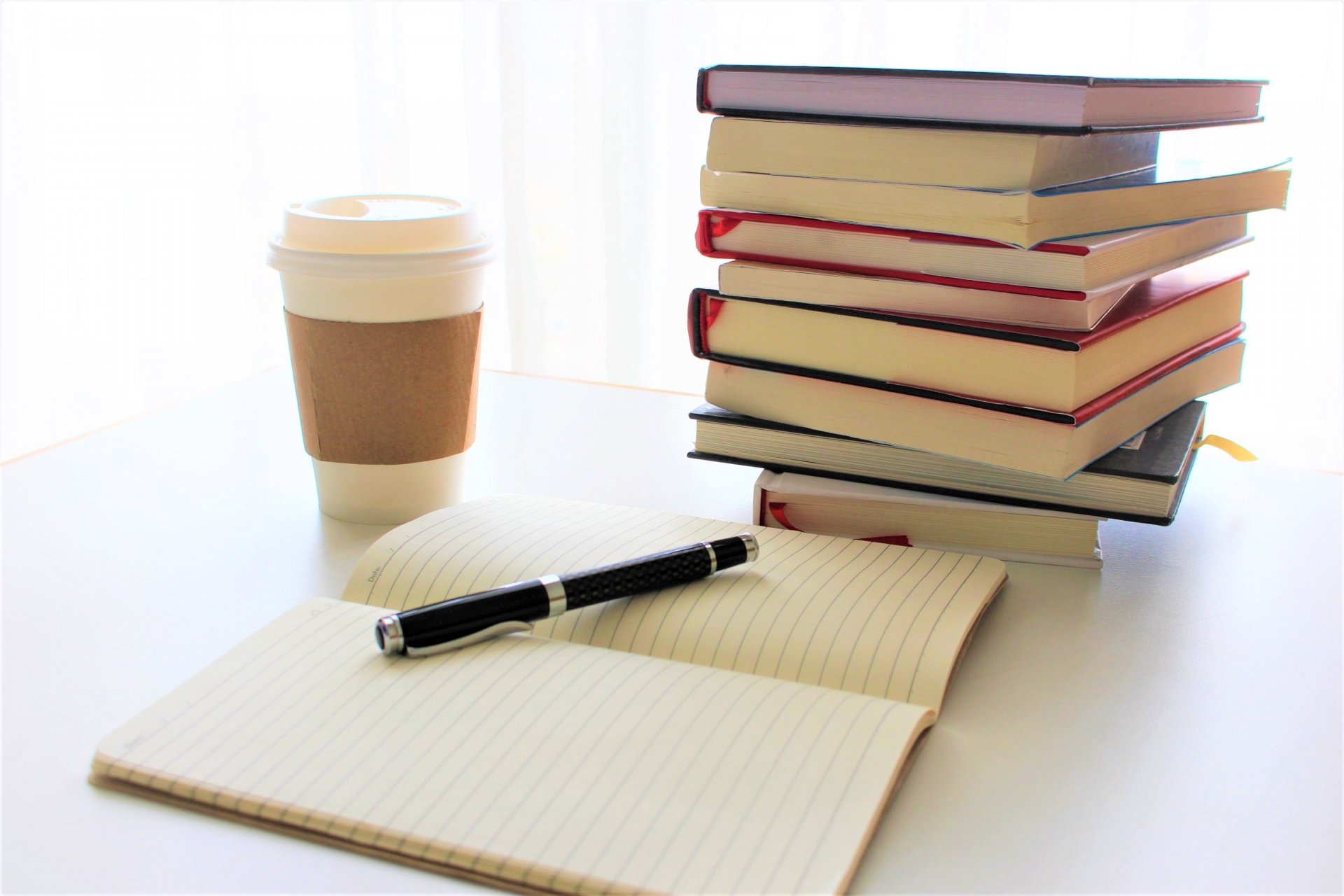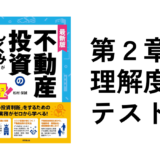不動産投資のしくみがわかる本、第1章の理解度テストアプリです。
完全マスターを目指して、繰り返しチャレンジしてみて下さい。
不動産投資 第1章
学習クイズアプリ
『ビジネス図解 不動産投資のしくみがわかる本』第1章の理解度をテストします。
挑戦するレベルを選択してください。
クイズ終了!
あなたのスコアは…
最終確認テスト
アプリで取り上げられている全問題を掲載しておきます。
最終確認テストにはこちらをご利用ください。
【初級編】(全20問)
基本的な用語や概念の理解度をチェックします。
問1. 不動産を他人に貸して継続的に得る賃料収入のことを何と呼びますか?
- キャピタルゲイン
- インカムゲイン
- レバレッジ
問2. 銀行が不動産投資に融資をしやすい主な理由は何ですか?
- 投資家の年収が高いから
- 不動産投資が国に推奨されているから
- 投資対象の不動産が担保になるから
問3. 保有していた資産を売却することによって得られる売却差益のことを何と呼びますか?
- キャピタルゲイン
- インカムゲイン
- デフォルト
問4. 不動産投資において、購入から運営、売却までの一連の計画のうち、特に売却に関する計画を何と呼びますか?
- 入口戦略
- 運営戦略
- 出口戦略
問5. 不動産価格の変動について、本書で述べられている傾向として正しいものはどれですか?
- 上がるときは急激で、下がるときはじんわり
- 上がるときはじんわりで、下がるときは急激
- 上がるときも下がるときも同じスピード
問6. 一般的に、不動産の「買いどき」とされる経済状況はどれですか?
- 景気が良く、金利が高いとき
- 景気が悪く、金利が低いとき
- 景気が良く、金利が低いとき
問7. 今後の日本の不動産投資市場を予測する上で、本書が重要キーワードとして挙げているものは「人口減少」ともう一つは何ですか?
- AI技術の進化
- インバウンド消費
- サブスクリプション経済
問8. 海外の投資家から見て、日本国内の不動産が割安となり、価格が上昇する要因となるのはどちらですか?
- 円高
- 円安
- 株価下落
問9. 金利が上昇すると、不動産価格は一般的にどうなりますか?
- 上がる
- 下がる
- 変わらない
問10. 不動産投資で発生するリスクとして、適切でないものはどれですか?
- 空室リスク
- 災害リスク
- 上場廃止リスク
問11. リスクを避けるための最善の方法として、本書が最も重要視していることは何ですか?
- 有名な投資家の意見に従うこと
- とにかく多くの物件を購入すること
- 正しい知識を身につけ、合理的な判断をすること
問12. 投資家から集めた資金で不動産に投資し、その収益を分配する金融商品のことをアルファベット4文字で何と呼びますか?
- NISA
- iDeCo
- REIT
問13. REIT(不動産投資信託)のメリットとして正しいものはどれですか?
- 実物不動産投資より利回りが高い
- 少額から投資が可能で手間がかからない
- 倒産するリスクが全くない
問14. 近年注目されている民泊投資のメリットとして、本書が挙げているものはどれですか?
- 手間がほとんどかからない
- 近隣トラブルが起きにくい
- 低資金で始められ、利回りが高くなりやすい
問15. 株式投資と比較した場合の不動産投資の特徴として、適切でないものはどれですか?
- 価格変動が緩やかである
- 流動性が高い(現金に換えやすい)
- 事業としての側面が強い
問16. (○か×か)不動産投資は、安く買って高く売ることだけが重要であり、保有期間中の運営ノウハウはあまり必要ないとされる。
問17. (○か×か)不動産投資で成功している人は全体の8割以上を占め、リスクは低いと言える。
問18. (○か×か)民泊を始めるには、必ず自分で不動産を購入する必要がある。
問19. (○か×か)不動産投資の出口戦略は、購入後に考え始めても遅くはない。
問20. (○か×か)経済指標を参考にすることは重要だが、あまり複雑に考えすぎると投資判断ができなくなるため、大まかな方向性を把握できればよい。
【上級編】(全20問)
知識の応用力や、より深い内容の理解度をチェックします。
問1. 価格5,000万円、実質利回り8%の物件を、自己資金1,000万円、借入金4,000万円(金利3%)で購入した場合、自己資金に対する利回りは何%になりますか?
- 8%
- 20%
- 28%
問2. 次のAとBの事例で、5年間のトータルリターン(インカムゲイン+キャピタルゲイン)がより高いのはどちらですか?(諸費用・税金は考慮しない)
A: 購入価格5,000万円、売却価格4,000万円、実質利回り10%
B: 購入価格5,000万円、売却価格6,000万円、実質利回り5%
- A
- B
- どちらも同じ
問3. 「実質利回り<支払金利」という状況になった場合、レバレッジはどのように作用しますか?
- プラス方向に作用し、利益が増幅される
- 作用しなくなり、影響はゼロになる
- マイナス方向に作用し、損失が拡大する
問4. 著者は、不動産投資で明確に成功していると言える人の割合を、どの程度だと推測していますか?
- 8割程度
- よくてせいぜい5割程度
- 2割程度
問5. 著者が「リスクを避けるための最善の方法」として知識の習得を挙げる中で、情報をインプットする際に特に重要だと述べていることは何ですか?
- なるべく多くの個人の成功体験談を読むこと
- 客観的事実と個人の意見や主張を明確に区別すること
- 税理士などの専門家が発信する情報のみを信じること
問6. 今後の不動産投資市場について、著者の見解として最も適切なものはどれですか?
- 人口減少が著しい地方でも、利回りが高ければ積極的に投資すべきである
- 地方であっても、インバウンド消費が見込める観光資源が豊富な場所は可能性がある
- 今後はインバウンド消費が減少するため、都市部への投資も危険である
問7. 景気動向指数が上昇し、円安が進んでいる状況は、不動産価格にどのような影響を与えると予測されますか?
- 景気動向指数は価格を押し上げ、円安は価格を押し下げるため、影響は相殺される
- 両方の要因が価格を押し下げる方向に働く
- 両方の要因が価格を押し上げる方向に働く
問8. REITへの投資経験は、実物不動産投資を行なう上でどのように役立つと著者は述べていますか?
- 実物不動産投資のシミュレーションとして非常に役立つ
- 役立つことはほとんどない
- REITで利益を出せなければ、実物不動産投資はやるべきではない
問9. 株式投資と比較して、不動産投資の投資額が大きくなりやすいことについて、著者はどのような警鐘を鳴らしていますか?
- 投資額が大きい分、リターンも大きいので問題ない
- 他の投資なら躊躇するリスク許容度の人が、不動産投資では平気で大きな投資をしてしまう傾向がある
- 投資額が大きいので、必ず専門家に任せるべきである
問10. 民泊の3つの種類(簡易宿所、特区民泊、新法民泊)のうち、営業日数の制限が「年間180日」と定められているのはどれですか?
- 簡易宿所
- 特区民泊
- 新法民泊
問11. 不動産投資に必要な知識分野として、本書が挙げている3つの柱は「不動産の実務」「法律」とあと一つは何ですか?
- マーケティング
- 金融工学
- 税金
問12. 著者が「出口戦略」の検討方法として推奨しているのはどのようなアプローチですか?
- 購入から5年後の売却価格だけを正確に予測する
- 複数の売却時期を設定し、それぞれの収益をシミュレーションする
- インカムゲインが最大化する時期を売却時期とする
問13. 不動産価格が「下がるときは急激に下がる」傾向があるため、売りどきの判断で特に注意すべきことは何だと述べられていますか?
- なるべく早く売却すること
- 「まだ価格が上がるのでは」と欲をかきすぎないこと
- 価格が下がり始めてから売却を検討すること
問14. 著者がコラムで「不動産投資で失敗している人に共通していること」として挙げているのは何ですか?
- 運が悪かったこと
- 勉強不足であること
- 自己資金が少なかったこと
問15. 融資を利用してレバレッジをかける不動産投資において、収益を圧迫し赤字になる可能性があるのは、どのような関係性が成立したときですか?
- 実質利回り > 支払金利
- 実質利回り < 支払金利
- 実質利回り = 支払金利
問16. (穴埋め)小さな力で大きなものを動かす、つまり( ① )を利用することで( ② )を高めることをレバレッジという。
問17. (穴埋め)民泊の集客で最初に利用すべきOTAとして、本書が挙げているのは( )である。
問18. (穴埋め)景気動向指数のうち、50%を上回っている時に景気がよくなっていると捉える指標は( )である。
問19. (穴埋め)不動産投資のリスクは、複数のものが( )的に発生することもよくある。
問20. (穴埋め)株式、債券、不動産などといった投資対象となる資産の分類のことを( )という。
解答と解説
【初級編】
解答1:2. インカムゲイン(P.18)
解説:不動産を保有している間に得られる収益がインカムゲインです。家賃収入がこれにあたります。
解答2:3. 投資対象の不動産が担保になるから(P.16)
解説:銀行は、万が一返済が滞っても不動産を差し押さえることで貸付金を回収できるため、他の投資よりも融資をしやすいのです。
解答3:1. キャピタルゲイン(P.18)
解説:不動産を購入価格より高く売却できた場合の利益がキャピタルゲインです。
解答4:3. 出口戦略(P.20)
解説:不動産投資は売却して初めて利益が確定するため、いつ、どのように売るかという出口戦略を事前に考えることが重要です。
解答5:2. 上がるときはじんわりで、下がるときは急激(P.22-23)
解説:この価格変動の特性を理解しておくことは、売りどきを逃さないために重要です。
解答6:2. 景気が悪く、金利が低いとき(P.22)
解説:景気が悪いと不動産価格は安くなり、金利が低いと借入コストが下がるため、投資家にとっては有利な状況となります。
解答7:2. インバウンド消費(P.24)
解説:訪日外国人観光客による消費(インバウンド消費)は、宿泊需要などを通じて不動産市場に影響を与えます。
解答8:2. 円安(P.26)
解説:円安になると、海外の投資家は自国通貨で日本の不動産を安く買えるため、需要が高まり価格上昇の要因となります。
解答9:2. 下がる(P.26)
解説:金利が上がると、ローンを組んで不動産を買う人の資金調達コストが上がるため、購入意欲が減退し、価格は下がる傾向にあります。
解答10:3. 上場廃止リスク(P.28, 32)
解説:上場廃止リスクは、株式市場に上場しているREIT(不動産投資信託)特有のリスクであり、実物の不動産投資には当てはまりません。
解答11:3. 正しい知識を身につけ、合理的な判断をすること(P.30)
解説:著者は、成功するためには他人の意見に流されず、自ら学んだ知識に基づいて判断することの重要性を強調しています。
解答12:3. REIT(P.32)
解説:REITは “Real Estate Investment Trust” の略で、不動産投資信託を指します。
解答13:2. 少額から投資が可能で手間がかからない(P.32)
解説:REITは運用のプロに任せられるため手間がかからず、証券として売買されるため少額から投資できるのがメリットです。
解答14:3. 低資金で始められ、利回りが高くなりやすい(P.34)
解説:民泊は物件を賃貸して始めることもできるため初期投資を抑えやすく、通常の賃貸より高い収益を狙える可能性があります。
解答15:2. 流動性が高い(現金に換えやすい)(P.38)
解説:不動産は買い手を見つけて契約し、決済するまでに時間がかかるため、株式のようにすぐに現金化できる「流動性」は低いです。
解答16:×(P.14)
解説:不動産投資は、保有期間中の物件管理や入居者対応といった運営ノウハウも収益に大きく影響します。
解答17:×(P.28)
解説:著者は、不動産投資で明確に成功している人は「よくてせいぜい5割程度」と推測しており、決して簡単な投資ではないことを示唆しています。
解答18:×(P.34)
解説:民泊は、既存の物件を賃借して(借りて)始めることも可能であり、これが低資金で始められる理由の一つです。
解答19:×(P.20)
解説:出口戦略は投資の利益を確定させる重要な要素であり、購入を判断する前にしっかりと検討しておくべきです。
解答20:○(P.27)
解説:経済指標は不動産価格の動向を予測する上で重要ですが、細部にこだわりすぎず、大局観を持つことが大切です。
【上級編】
解答1:3. 28%(P.16-17)
解説:年間の収益は(5,000万円 × 8%) – (4,000万円 × 3%) = 280万円。これを自己資金1,000万円で割ると、280万円 ÷ 1,000万円 = 28% となります。
解答2:2. B(P.19)
解説:Aのトータルリターンは(5000万×10%×5年) + (4000万 – 5000万) = 1500万円。Bは(5000万×5%×5年) + (6000万 – 5000万) = 2250万円。インカムゲインが低くても、キャピタルゲインが大きいBの方がトータルリターンは高くなります。
解答3:3. マイナス方向に作用し、損失が拡大する(P.17)
解説:借入金の金利が物件の収益率を上回ると、借金が利益を圧迫し、損失を増幅させる「負のレバレッジ」がかかります。
解答4:2. よくてせいぜい5割程度(P.28)
解説:著者は、収支トントンが3割、赤字が2割いると推測しており、不動産投資の厳しさを示しています。
解答5:2. 客観的事実と個人の意見や主張を明確に区別すること(P.30-31)
解説:特に個人の成功体験談は、その人特有の状況によるものが多く、万人に当てはまる客観的な事実ではないため、鵜呑みにするのは危険だと著者は指摘しています。
解答6:2. 地方であっても、インバウンド消費が見込める観光資源が豊富な場所は可能性がある(P.24)
解説:人口減少というマイナス要因があっても、インバウンドというプラス要因が期待できるエリアは、投資対象として検討の余地があると述べられています。
解答7:3. 両方の要因が価格を押し上げる方向に働く(P.26-27)
解説:景気動向指数の上昇は景気が良いことを示し、円安は海外からの投資を呼び込むため、両者とも不動産価格の上昇要因となります。
解答8:2. 役立つことはほとんどない(P.32)
解説:REITは金融商品としての側面が強く、実物の不動産を取得・運営するノウハウは身につかないため、実物投資への応用は難しいとされています。
解答9:2. 他の投資なら躊躇するリスク許容度の人が、不動産投資では平気で大きな投資をしてしまう傾向がある(P.39)
解説:著者は、投資額の大きさに感覚が麻痺し、自分のリスク許容度を超えた投資をしてしまう危険性を指摘しています。
解答10:3. 新法民泊(P.35)
解説:2018年に施行された住宅宿泊事業法(新法民泊)では、営業日数が年間180日に制限されています。
解答11:3. 税金(P.15)
解説:不動産投資を成功させるには、実務、法律、税金の3つの分野の知識が不可欠であると述べられています。
解答12:2. 複数の売却時期を設定し、それぞれの収益をシミュレーションする(P.20)
解説:将来の価格予測は困難なため、例えば「5年後、10年後、15年後に売却した場合」など、複数のシナリオで収益を比較検討することが有効です。
解答13:2. 「まだ価格が上がるのでは」と欲をかきすぎないこと(P.22)
解説:価格が下がり始めると急落する可能性があるため、天井値で売ろうと欲をかくと、売りどきを逃してしまうリスクが高いと指摘されています。
解答14:2. 勉強不足であること(P.40)
解説:失敗の根本的な原因は、知識不足のまま営業マンの言うことを鵜呑みにしてしまうなど、自ら判断する努力を怠っていることにあると著者は述べています。
解答15:2. 実質利回り < 支払金利(P.17)
解説:物件が生み出す収益率(実質利回り)が、借入金の利息(支払金利)を下回ると、返済が収益を上回り、持ち出し(赤字)が発生します。
解答16:① 借入金、② 利益率(P.17)
解説:レバレッジは「てこの原理」とも言われ、借入金(他人資本)を利用して自己資金に対する利益率を高める効果を指します。
解答17:Airbnb(エアービーアンドビー)(P.36)
解説:民泊の集客はOTA(オンライン・トラベル・エージェント)で行うのが主で、その中でも世界的に利用者が多いAirbnbを最初に利用すべきだと推奨されています。
解答18:DI(ディフューザー・インデックス)(P.27)
解説:DIは景気指標の動向を合成したもので、景気の方向感を示します。50%が好不況の分岐点とされます。
解答19:重畳(ちょうじょう)(P.29)
解説:「重畳的」とは、物事が幾重にも重なる様子のことです。例えば、空室リスクが家賃下落リスクを呼び、それが不動産価格下落リスクにつながる、というようにリスクが連鎖することを指します。
解答20:資産クラス(アセットクラス)(P.33)
解説:投資の世界では、リスクや値動きの特性が似ている資産をグループ化したものを資産クラスと呼び、分散投資を考える際の基本となります。
解説を読んでみても、よくわからない問題については、あらためて書籍の該当箇所を確認してみて下さい。