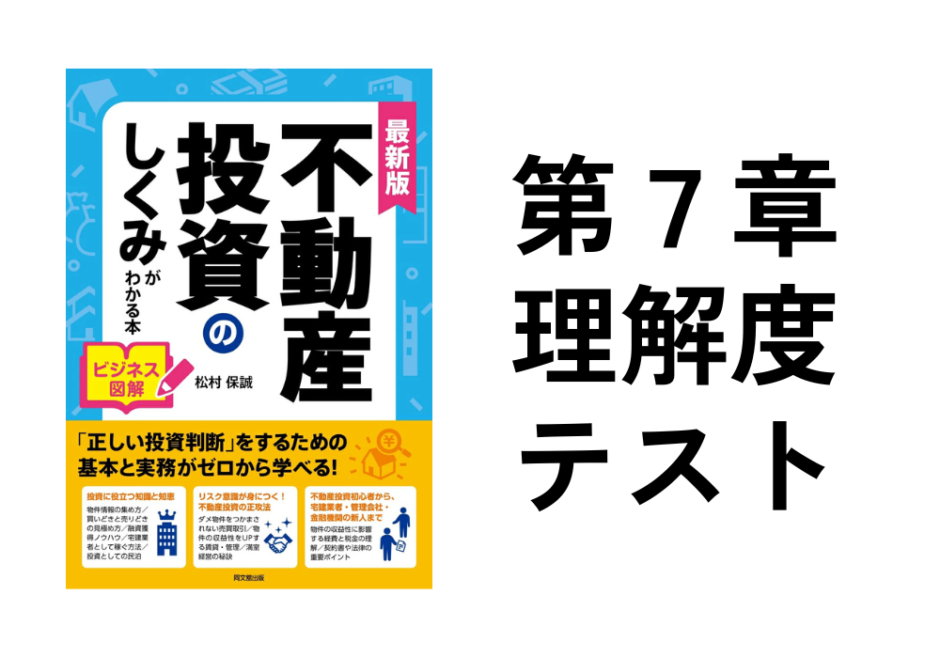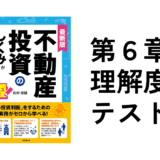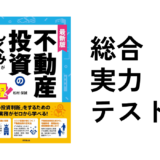不動産投資のしくみがわかる本、第7章の理解度テストアプリです。
完全マスターを目指して、繰り返しチャレンジしてみて下さい。
不動産投資 第7章
学習クイズアプリ
『ビジネス図解 不動産投資のしくみがわかる本』第7章の理解度をテストします。
挑戦するレベルを選択してください。
クイズ終了!
あなたのスコアは…
最終確認テスト
アプリで取り上げられている全問題を掲載しておきます。
最終確認テストにはこちらをご利用ください。
【初級編】(全20問)
税金に関する基本的な知識や用語の理解度をチェックします。
問1. 個人で不動産投資を行い、保有している間に得られる所得を何といいますか?
- 譲渡所得
- 不動産所得
- 事業所得
問2. 不動産所得のように、給与所得など他の所得と合算して税額が計算される課税方式を何といいますか?
- 分離課税
- 源泉徴収
- 総合課税
問3. 不動産所得で赤字が出た場合に、給与所得などの黒字からその赤字分を差し引くことができる制度を何といいますか?
- 損益通算
- 所得控除
- 税額控除
問4. 不動産を売却して得た利益(売却益)のことを、税法上何といいますか?
- キャピタルゲイン
- 譲渡所得
- 売却所得
問5. 不動産の譲渡所得は、給与所得などとは合算せずに、それ単独で税金が計算されます。この課税方式を何といいますか?
- 総合課税
- 分離課税
- 申告納税
問6. 不動産を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える場合の譲渡所得を何といいますか?
- 短期譲渡所得
- 長期譲渡所得
- 一般譲渡所得
問7. 株式会社などの法人を設立して不動産投資を行う場合、法人の所得に対して課される中心的な国税を何といいますか?
- 法人事業税
- 法人税
- 法人住民税
問8. 納税者の個人的事情(扶養家族がいる、生命保険料を払っているなど)に応じて、所得金額から一定額を差し引くことができるものを何といいますか?
- 所得控除
- 必要経費
- 損金算入
問9. 居住する都道府県や市区町村に納める地方税で、前年の所得額に応じて計算される「所得割」がある税金は何ですか?
- 所得税
- 固定資産税
- 住民税
問10. 個人で不動産貸付業などを行う場合に、所得金額が一定額を超えると課される都道府県税を何といいますか?
- 個人事業税
- 個人住民税
- 特別所得税
問11. 著者が、不動産投資において税額の予測計算が必要だと述べる最も大きな理由は何ですか?
- 税務署に提出するため。
- 実際に手元に残る現金の額がわからないから。
- 金融機関に融資を申し込む際の必須書類だから。
問12. 不動産投資を個人で行う場合と法人で行う場合とで、有利不利の判断はどうなると述べられていますか?
- 必ず個人が有利になる。
- 必ず法人が有利になる。
- ケースバイケースである。
問13. 法人を設立して不動産投資を行う場合、個人での投資に比べて追加で必要となる費用は何ですか?
- 仲介手数料
- 登記費用
- 法人設立費用や税理士報酬
問14. (○か×か)不動産所得の計算上、建物の購入代金は、減価償却費として複数年にわたって経費に計上できる。
問15. (○か×か)不動産を売却して損失が出た場合、その損失は給与所得と損益通算することができる。
問16. (○か×か)所得税の税率は、所得金額にかかわらず全員一律である。
問17. (○か×か)法人税は、赤字であれば支払う必要はないが、法人住民税の「均等割」は赤字でも支払う必要がある。
問18. (○か×か)個人事業税は、所得税や住民税と違い、経費として計上することはできない。
問19. (○か×か)不動産投資で所得が増えると、所得税だけでなく住民税も増加する。
問20. (○か×か)法人が役員に支払う役員報酬は、税務計算上、経費(損金)として認められない。
【上級編】(全20問)
より専門的な知識や、税額計算に関する深い理解度をチェックします。
問1. 不動産所得の赤字を損益通算する際、通算の対象とならないものは次のうちどれですか?
- 建物部分の減価償却費
- 土地購入のための借入金の利子部分
- 建物の修繕費
問2. 正規の簿記の原則に従って確定申告を行う「青色申告」の特典として、本書で挙げられているものはどれですか?
- 最高55万円の青色申告特別控除と、損失の3年間の繰越控除。
- 所得税率が常に半分になる。
- 住民税が全額免除される。
問3. 所得税と住民税の所得控除額を比較した場合、一般的にどのような違いがありますか?
- 住民税の控除額の方が大きい。
- 所得税の控除額の方が大きい。
- どちらも全く同じ金額である。
問4. 個人事業税(不動産貸付業)の税率は何%ですか?
- 3%
- 5%
- 10%
問5. 2020年3月1日に不動産を購入し、2025年12月1日に売却した場合、譲渡所得の区分はどうなりますか?
- 実質的な所有期間が5年を超えるため、長期譲渡所得となる。
- 売却した年の1月1日時点では所有期間が5年以下のため、短期譲渡所得となる。
- 所有期間にかかわらず、常に長期譲渡所得となる。
問6. 資本金1億円以下の法人の法人税率に関する説明で、正しいものはどれですか?
- 課税所得の金額にかかわらず、一律23.20%である。
- 課税所得のうち年800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は23.20%である。
- 課税所得のうち年800万円以下の部分は23.20%、800万円超の部分は15%である。
問7. 法人が納める税金のうち、翌年の経費(損金)に算入できるものはどれですか?
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
問8. 個人と法人のどちらが有利かを比較検討する際に、考慮すべき要素として「適切でない」ものはどれですか?
- 不動産保有時・売却時の税金
- 法人設立費用や税理士報酬
- 物件の所在地
問9. 法人から個人へ役員報酬という形でお金を移した場合、税金はどのように変化しますか?
- 法人の所得が減り法人税は安くなるが、個人の所得が増え所得税・住民税は高くなる。
- 法人税も個人の所得税も両方安くなる。
- 法人税も個人の所得税も両方高くなる。
問10. 中古建物の耐用年数が法定耐用年数を超えている場合、その耐用年数はどのように計算しますか?
- 2年とする。
- 法定耐用年数 × 0.2 で計算する。
- 法定耐用年数と同じ年数とする。
問11. 譲渡所得の計算式「譲渡価格 − 取得費 − 譲渡費用」において、「取得費」に含まれないものはどれですか?
- 不動産の購入代金(建物は減価償却後の価額)
- 購入時の仲介手数料
- 売却時の仲介手数料
問12. 短期譲渡所得の場合の所得税と住民税を合わせた税率は何%ですか?
- 20%
- 30%
- 39%
問13. 個人事業税の計算において、所得税の計算と異なる特徴的な点は何ですか?
- 青色申告特別控除が適用されず、代わりに290万円の事業主控除がある。
- 基礎控除の金額が所得税より大きい。
- 扶養控除が2倍になる。
問14. 著者がコラムで、物件内での死亡事故の告知について、自身の経験から得た教訓として述べていることは何ですか?
- 法律上の告知義務の有無を厳密に判断し、義務がなければ伝える必要はない。
- 確実にトラブルを避けたいなら、借主が気になるかもしれないことは伝えておくほうがいい。
- 告知は不動産屋の責任であり、家主は関与すべきではない。
問15. 課税所得650万円の人が、不動産投資により所得が100万円増加して750万円になった場合、所得税はいくら増加しますか?(本書P.197の速算表を参照)
- 10万円
- 20万円
- 21万6500円
問16. (穴埋め)地方ごとの財政格差を是正する目的で導入された国税には、( )と地方法人税がある。
問17. (穴埋め)譲渡所得の計算で取得費が不明な場合、譲渡価額の( )%を概算取得費とすることができる。
問18. (穴埋め)法人の会計処理では、収益を( ① )、費用を( ② )と呼び、それぞれに税務上の調整を行って課税所得を計算する。
問19. (穴埋め)法人住民税は、法人税額に応じて計算される( ① )割と、資本金や従業員数に応じて定額で課される( ② )割からなる。
問20. (穴埋め)著者はコラムで、リスクを抑えて不動産投資を始める方法として、自己居住用として( )で購入した物件を、完済後に賃貸に出すことを繰り返す方法を挙げている。
解答と解説
【初級編】
解答1:2. 不動産所得(P.194)
解説:家賃収入など、不動産の貸付によって得られる所得を不動産所得といいます。
解答2:3. 総合課税(P.194)
解説:複数の種類の所得を合算して、一つの課税所得として税額を計算する方法です。
解答3:1. 損益通算(P.194)
解説:特定の所得の赤字を他の所得の黒字と相殺できる制度です。不動産所得の赤字は、給与所得などと損益通算できます。
解答4:2. 譲渡所得(P.200)
解説:土地、建物、株式などを売却(譲渡)した際に生じる所得のことです。
解答5:2. 分離課税(P.200)
解説:他の所得とは切り離して(分離して)、独自の税率で税額を計算する方法です。
解答6:2. 長期譲渡所得(P.200)
解説:所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わります。長期の方が税率は低くなります。
解答7:2. 法人税(P.202)
解説:法人の各事業年度の所得に対して課される国税で、法人にかかる税金の中核をなします。
解答8:1. 所得控除(P.196)
解説:基礎控除、配偶者控除、扶養控除など14種類あり、納税者の担税力に応じて税負担を調整する役割があります。
解答9:3. 住民税(P.198)
解説:所得割と、所得にかかわらず定額で課される均等割から構成されています。
解答10:1. 個人事業税(P.198)
解説:不動産貸付業や駐車場業なども事業と見なされ、所得が290万円の事業主控除を超えると課税対象となります。
解答11:2. 実際に手元に残る現金の額がわからないから。(P.192)
解説:表面的な収入から経費を引いただけでは、税金の負担が考慮されていません。税引き後のキャッシュフローを把握するために、税額計算は不可欠です。
解答12:3. ケースバイケースである。(P.206)
解説:所得の金額、保有期間、売却のタイミングなど、様々な条件によってどちらが有利になるかは変わるため、一概には言えません。
解答13:3. 法人設立費用や税理士報酬(P.206)
解説:法人は設立に費用がかかり、また、税務申告が複雑なため税理士への報酬が必要になることが多く、これらが追加コストとなります。
解答14:○(P.201)
解説:建物の取得価額を法定耐用年数で割り、毎年少しずつ経費として計上します。これを減価償却といいます。
解答15:×(P.200)
解説:不動産の譲渡による損失は、原則として他の所得(給与所得など)と損益通算することはできません。
解答16:×(P.196)
解説:所得税は、所得が多くなるほど税率が高くなる「累進課税制度」が採用されています。
解答17:○(P.202)
解説:法人住民税の均等割は、法人が存在していること自体に対して課される税金なので、事業が赤字でも納税義務があります。
解答18:×(P.199)
解説:個人事業税は、所得税の確定申告において、全額を必要経費として計上することができます。
解答19:○(P.198)
解説:住民税の所得割は前年の所得に基づいて計算されるため、不動産投資で所得が増えれば、翌年の住民税も増加します。
解答20:×(P.206)
解説:法人が役員に支払う役員報酬は、一定のルールのもとで経費(損金)として認められ、法人の所得から差し引くことができます。
【上級編】
解答1:2. 土地購入のための借入金の利子部分(P.195)
解説:不動産所得の赤字のうち、土地を取得するために借り入れたお金の利子に相当する部分は、損益通算の対象から除外されるというルールがあります。
解答2:1. 最高55万円の青色申告特別控除と、損失の3年間の繰越控除。(P.194, 195)
解説:青色申告には税制上の大きなメリットがあり、不動産所得や事業所得がある場合は活用すべき制度です。
解答3:2. 所得税の控除額の方が大きい。(P.199)
解説:基礎控除や配偶者控除など、多くの所得控除項目で、所得税の控除額の方が住民税の控除額よりも高く設定されています。
解答4:2. 5%(P.198)
解説:不動産貸付業の個人事業税の税率は5%と定められています。
解答5:2. 売却した年の1月1日時点では所有期間が5年以下のため、短期譲渡所得となる。(P.200)
解説:実際の所有期間ではなく、「譲渡した年の1月1日」を基準に判定するという点が重要です。このケースでは2025年1月1日時点で5年を超えていないため、短期となります。
解答6:2. 課税所得のうち年800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は23.20%である。(P.202)
解説:中小法人には軽減税率が適用され、所得金額に応じて2段階の税率が適用されます。
解答7:3. 法人事業税(P.204)
解説:法人事業税と特別法人事業税は、支払った事業年度の翌事業年度に損金算入できます。法人税や法人住民税は損金に算入できません。
解答8:3. 物件の所在地(P.206)
解説:物件の所在地は、固定資産税などには影響しますが、個人と法人のどちらが税務上有利かを判断する直接的な要素ではありません。
解答9:1. 法人の所得が減り法人税は安くなるが、個人の所得が増え所得税・住民税は高くなる。(P.206)
解説:役員報酬を活用することで、法人と個人の所得を調整し、トータルでの税負担を最適化する「所得分散」の効果が期待できます。
解答10:2. 法定耐用年数 × 0.2 で計算する。(P.201)
解説:例えば、法定耐用年数22年の木造住宅で築30年の物件を取得した場合、耐用年数は22年×0.2=4.4年→4年となります。(1年未満は切り捨て)
解答11:3. 売却時の仲介手数料(P.200)
解説:売却時の仲介手数料は、売却するために直接かかった費用である「譲渡費用」に分類されます。「取得費」は、その不動産を取得するためにかかった費用です。
解答12:3. 39%(P.200)
解説:税率の内訳は、所得税が30%、住民税が9%です。長期譲渡所得(所得税15%、住民税5%の計20%)に比べてかなり高い税率が課されます。
解答13:1. 青色申告特別控除が適用されず、代わりに290万円の事業主控除がある。(P.198)
解説:個人事業税の計算では、所得税の青色申告特別控除額を所得に足し戻し、そこから一律290万円の事業主控除を差し引いて課税所得を算出します。
解答14:2. 確実にトラブルを避けたいなら、借主が気になるかもしれないことは伝えておくほうがいい。(P.190)
解説:法律論だけでなく、入居者の心情を考慮し、後々のトラブルを避けるという観点から、透明性のある対応を推奨しています。
解答15:3. 21万6500円(P.197)
解説:所得税は累進課税のため、所得が増えるとより高い税率が適用されます。このケースでは、所得の増加分100万円に対して、税率が10%から20%に、さらに一部が23%になるため、税金の増加額は単純な計算より大きくなります。
解答16:特別法人事業税(P.204)
解説:この2つの税金は国税として徴収された後、地方交付税として財政力の弱い地方自治体に再分配されます。
解答17:5(P.200)
解説:売買契約書などを紛失して実際の取得費が証明できない場合に、売却額の5%を取得費とみなして計算することが認められています。
解答18:① 益金、② 損金(P.202)
解説:法人の課税所得は「益金 − 損金」で計算されます。これは個人の「総収入金額 − 必要経費」に相当する考え方です。
解答19:① 法人税、② 均等(P.202)
解説:法人税割は黒字の時に法人税額に応じて発生し、均等割は赤字でも法人が存在する限り発生します。
解答20:住宅ローン(P.208)
解説:自己居住用の住宅ローンは、投資用ローンに比べて金利が低く、審査も通りやすいというメリットを活用した、リスクの低い資産形成術として紹介されています。
解説を読んでみても、よくわからない問題については、あらためて書籍の該当箇所を確認してみて下さい。