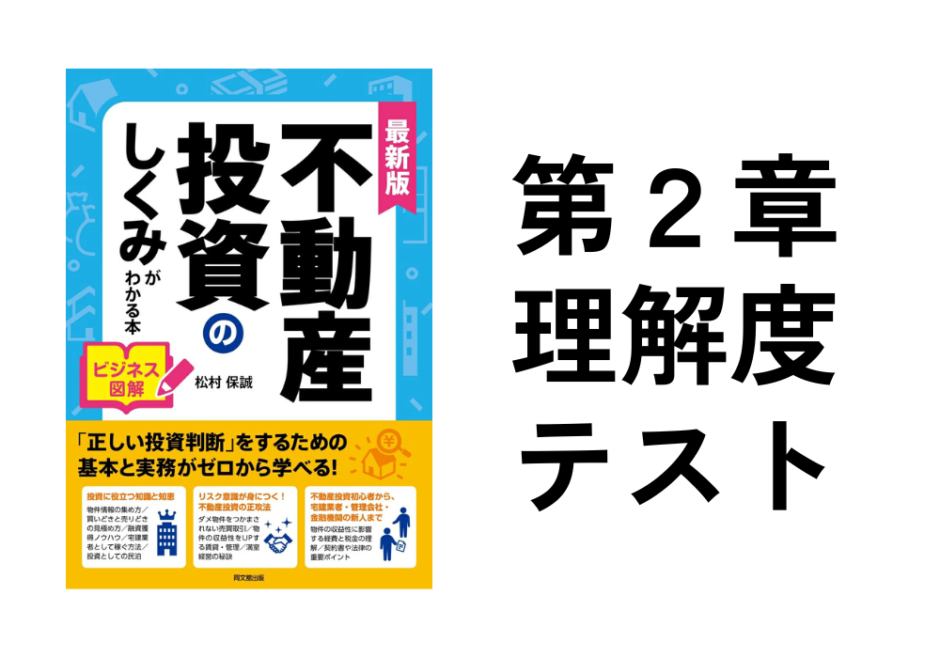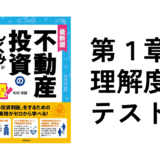不動産投資のしくみがわかる本、第2章の理解度テストアプリです。
完全マスターを目指して、繰り返しチャレンジしてみて下さい。
不動産投資 第2章
学習クイズアプリ
『ビジネス図解 不動産投資のしくみがわかる本』第2章の理解度をテストします。
挑戦するレベルを選択してください。
クイズ終了!
あなたのスコアは…
最終確認テスト
アプリで取り上げられている全問題を掲載しておきます。
最終確認テストにはこちらをご利用ください。
【初級編】(全20問)
基本的な用語や取引の流れに関する理解度をチェックします。
問1. 不動産取引の大まかな流れの中で、「購入申し込み」の次に行うことは何ですか?(融資を利用する場合)
- 契約を締結する
- 決済および引渡し
- 金融機関の事前審査を受ける
問2. 宅地建物取引業者(不動産屋さん)が物件情報の交換をするためのネットワークシステムのことを何と呼びますか?
- ホームズ
- レインズ
- スーモ
問3. 物件を購入したいという意思を固めた際に書面で行う申し込みのことを、不動産業界の慣習で何と呼びますか?
- 買い付け
- 先物買い
- 青田買い
問4. 売買契約を締結する前に、宅地建物取引士が買主に対して行わなければならない、物件に関する重要な説明のことを何と呼びますか?
- 契約内容報告
- 物件概要説明
- 重要事項説明
問5. 都市計画区域内で建物を建築する際、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない義務を何といいますか?
- 接道義務
- 建築義務
- 隣接義務
問6. 建築物の敷地面積に対する建築面積の割合のことを何と呼びますか?
- 容積率
- 建ぺい率
- 建築率
問7. 建築物の敷地面積に対する延床面積の割合のことを何と呼びますか?
- 容積率
- 建ぺい率
- 床面積率
問8. 不動産取引において、不動産屋さん自身が売主となる取引の態様を何といいますか?
- 代理
- 媒介(仲介)
- 売主
問9. 買主が売主に手付金を交付している場合、買主がその手付金を放棄することで契約を解除できることを何といいますか?
- 債務不履行解除
- 手付解除
- 契約不適合解除
問10. 引き渡された不動産に重大な故障など、契約の内容に適合しない点があった場合に、買主が売主に対して修補などを請求できる責任を何といいますか?
- 瑕疵担保責任
- 製造物責任
- 契約不適合責任
問11. 不人気物件で稼ぐ方法の一つとして本書で挙げられている、接道義務を満たさず建て直しができない物件を何といいますか?
- 既存不適格建築物
- 再建築不可物件
- 違法建築物
問12. 不動産屋さんの選び方のポイントとして、著者が最も重視していることの一つは何ですか?
- 店舗が大きいこと
- 誠実であるか
- 広告をたくさん出していること
問13. 物件を見学する際、隣地との境界を確認するために目印となるものは何ですか?
- 境界杭
- 電柱
- 側溝
問14. (○か×か)不動産取引の流れにおいて、購入申し込みをしたら、必ずその物件を購入しなければならない。
問15. (○か×か)良い物件情報を得るためには、不動産屋さんにしつこく営業されるのを恐れて連絡先を伝えない方がよい。
問16. (○か×か)不動産屋さんは「不動産のプロ」なので、投資判断についても全面的に依存して良い。
問17. (○か×か)物件見学の際、駅までの徒歩時間は物件資料の記載を信じればよく、自分で確認する必要はない。
問18. (○か×か)価格交渉をする際は、値引きを求める理由をつけないと成功しにくい。
問19. (○か×か)重要事項説明は、内容が分からなくてもその場の空気を読んで、分かったふりをして契約に進むべきである。
問20. (○か×か)売買契約書は、トラブルが発生した際の解決方法を定める重要な書類である。
【上級編】(全20問)
より専門的な知識や、著者の考え方に対する深い理解度をチェックします。
問1. 著者が「レインズ登録物件」について述べている見解として、最も適切なものはどれですか?
- レインズ登録物件は他の投資家が見送ったダメ物件ばかりなので、見る価値はない。
- 収益物件専門の不動産屋が登録した物件は、掘り出し物が多いので狙い目である。
- 不動産投資の知識が乏しい不動産屋が査定した、思わぬ好物件が見つかることもある。
問2. 著者が勧める、自己居住用物件の中から投資対象を探す際のポイントとして「適切でない」ものはどれですか?
- 3DK以下の広さの物件を中心に探す。
- 土地は原則、広いほうがよい。
- 築年数が古い物件を選ぶ。
問3. 著者が不人気物件の例として挙げた「既存不適格建築物」が安く購入できる主な理由は何ですか?
- 建て替えができないから。
- 住宅ローンを利用しにくく、現金購入できる買主に限られるから。
- 災害に非常に弱いから。
問4. 著者がコラムで述べた、重要事項説明の場で買主がとるべき態度として最も推奨されるものはどれですか?
- 専門用語が多くて分からないので、宅建士に全てを任せる。
- 疑問を感じたら、宅建士に遠慮せず、理解できるまで説明を求める。
- 説明が長くならないように、早めに切り上げてもらう。
問5. 宅建業を開業するために事務所に設置が必要な「専任の宅地建物取引士」の、従業員数に対する法定の割合はどれですか?
- 3名に1名以上
- 5名に1名以上
- 10名に1名以上
問6. 不動産屋が売り物件情報を得る方法として、著者が「特に積極的に交流すべき」としているのはどのような不動産屋ですか?
- 大手の不動産買取専門業者
- 自社では不動産の買取を行っていない不動産屋
- 新築物件のみを扱う不動産屋
問7. 取引態様が「売主」の物件について、著者の考えとして正しいものはどれですか?
- 仲介手数料が不要なので、必ず「媒介」より得になる。
- 取引の公平性が担保されないことがあるため、必ずしも得とは言えない。
- 買主は必ず媒介業者を入れなければならない。
問8. 区分所有マンションの共用部分の管理状況が悪い場合、著者はどうすべきだと述べていますか?
- 価格交渉の材料として積極的に購入を検討する。
- 購入後に自分で管理の質を改善すればよい。
- 一オーナーレベルで管理の質を変えるのは難しいため、購入は見送るのが無難。
問9. 金融機関から融資を受けられない場合に契約を無条件解除できる「ローン特約」を契約に付帯してほしい場合、いつその旨を伝える必要がありますか?
- 契約締結の直前
- 重要事項説明のとき
- 購入申込書を提出するとき
問10. 幅員4m未満の「2項道路」に接する土地に建物を再建築する場合、必要となる対応は何ですか?
- 特定行政庁から特別な許可を得る。
- 道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退(セットバック)させる。
- 再建築は一切認められない。
問11. 著者が「かしこい不動産屋さんとのつき合い方」として挙げていないものはどれですか?
- 言っていることを鵜呑みにしない。
- 投資判断について依存しない。
- 良好な関係を築くため、なるべく親しくなる。
問12. 自分で物件を管理する場合、著者が「必ず1社に固定するべき」と強く主張していることは何ですか?
- リフォームを依頼する業者
- 入居者募集の窓口となる不動産屋さん(媒介契約)
- 家賃保証会社
問13. 著者が、不動産屋さんの選び方(番外編)で「流しそうめん」に例えて説明していることは何ですか?
- 物件情報は次から次へと流れてくるので、焦る必要はないということ。
- 顧客が多い不動産屋では、優先順位の低い客には良い情報が回ってこないということ。
- 良い物件情報は、そうめんのように細く長く探し続けることが大事だということ。
問14. 建ぺい率の緩和措置が適用されるケースとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- 敷地が公園に隣接している場合
- 防火地域内にある耐火建築物の場合
- 3階建て以上の建築物の場合
問15. 違法建築物と既存不適格建築物の違いに関する説明で、正しいものはどれですか?
- 違法建築物とは、法改正により基準に適合しなくなった建物のことである。
- 既存不適格建築物とは、建築された当時から法令基準に抵触していた建物のことである。
- 既存不適格建築物とは、建築当時は適法だったが、その後の法改正で基準に適合しなくなった建物のことである。
問16. (穴埋め)不動産屋さんが仲介する場合の報酬である仲介手数料は( ① )報酬なので、成約できなければ不動産屋さんは1円も受け取ることができない。
問17. (穴埋め)自ら不動産屋になるための最初のステップとして、著者は( )試験に合格することを挙げている。
問18. (穴埋め)建物の再建築ができない「再建築不可物件」であっても、現状、建築確認申請が不要な範囲での( )は可能である。
問19. (穴埋め)重要事項説明書に記載される「( )区域」は、原則として建物の建築ができないため、基本的にはこの区域内の不動産は購入対象とすべきではない。
問20. (穴埋め)金融機関からの融資を利用して不動産を購入する場合、契約締結前に融資の可否について( )を受ける。
解答と解説
【初級編】
解答1:3. 金融機関の事前審査を受ける(P.42)
解説:契約後に融資が受けられないという事態を避けるため、契約前に金融機関の事前審査を受け、融資のめどを立てておきます。
解答2:2. レインズ(P.44)
解説:REINS(Real Estate Information Network System)は、宅建業者間の情報交換システムで、多くの物件情報が登録されています。
解答3:1. 買い付け(P.66)
解説:「不動産購入申込書」を提出することを、業界では「買い付けを入れる」などと呼びます。
解答4:3. 重要事項説明(P.68)
解説:宅地建物取引業法で義務付けられており、契約前に物件の権利関係や法令上の制限などを買主に説明する非常に重要な手続きです。
解答5:1. 接道義務(P.70)
解説:この義務を満たしていないと、原則として建物の再建築ができません。
解答6:2. 建ぺい率(P.72)
解説:「建蔽率」とも書きます。土地を上から見たときに、建物がどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。
解答7:1. 容積率(P.72)
解説:その土地に建てられる建物の延床面積(各階の床面積の合計)の上限を定めたものです。
解答8:3. 売主(P.60)
解説:不動産屋さんが自社で所有している物件を直接販売するケースです。この場合、買主は仲介手数料を支払う必要がありません。
解答9:2. 手付解除(P.76)
解説:契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金放棄、売主は手付金の倍額を返すことで、一方的に契約を解除できます。
解答10:3. 契約不適合責任(P.76)
解説:2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から変更されました。契約内容と違うものを売った場合の売主の責任です。
解答11:2. 再建築不可物件(P.48)
解説:建て替えができないため資産価値は低いと見なされがちですが、その分安く買えるため、高い利回りを狙える可能性があります。
解答12:2. 誠実であるか(P.50)
解説:物件や取引上の問題点を正直に話してくれるか、質問に真摯に答えてくれるかなど、顧客に対して誠実かどうかが最も重要です。
解答13:1. 境界杭(P.64)
解説:土地の境界を示すコンクリートや石の杭のことです。これが明確でないと、将来隣地とのトラブルの原因になることがあります。
解答14:×(P.67)
解説:購入申込書(買い付け)は売買契約書ではなく、提出後に売主の承諾が得られてから契約締結に進みます。
解答15:×(P.44)
解説:良い物件情報を得るためには、見込み客として認識してもらうことが重要なので、連絡先はしっかりと伝えるべきだと述べられています。
解答16:×(P.52)
解説:不動産屋さんは「不動産取引」のプロであり、「投資」のプロではないため、投資の最終判断は自分で行うべきだと著者は強調しています。
解答17:×(P.64)
解説:物件資料の記載が不正確なこともあるため、駅までの距離や時間は、自分の足で実際に確認することが重要です。
解答18:○(P.66)
解説:「外壁の修繕費がかかるので」など、具体的な理由を添えることで、売主も交渉に応じやすくなります。
解答19:×(P.68)
解説:高額な取引なので、内容を理解できないまま契約するのは非常に危険です。理解できるまで質問し、納得できなければ契約しない勇気が必要です。
解答20:○(P.77)
解説:売買契約は口頭でも成立しますが、後日のトラブルを防ぐために、手付解除や契約不適合責任などのルールを明記した契約書を交わします。
【上級編】
解答1:3. 不動産投資の知識が乏しい不動産屋が査定した、思わぬ好物件が見つかることもある。(P.46)
解説:著者は、全ての不動産屋が収益性を正しく評価できるわけではないため、レインズにも安値で放置された優良物件が存在する可能性があると指摘しています。
解答2:2. 土地は原則、広いほうがよい。(P.47)
解説:投資の観点では、土地が広くても家賃は大きく変わらないため、価格が安い狭い土地のほうが利回りは高くなる傾向にあります。
解答3:2. 住宅ローンを利用しにくく、現金購入できる買主に限られるから。(P.48)
解説:買主の層が限定されるため、売り手は価格交渉に応じざるを得ない状況になりやすく、安く購入できる可能性が高まります。
解答4:2. 疑問を感じたら、宅建士に遠慮せず、理解できるまで説明を求める。(P.78)
解説:著者はコラムで、内容を理解できない書類にハンコを押すべきではないとし、買主が説明を求めるのは当然の権利だと述べています。
解答5:2. 5名に1名以上(P.54)
解説:宅地建物取引業法で定められており、不動産屋を開業するための重要な要件の一つです。
解答6:2. 自社では不動産の買取を行っていない不動産屋(P.58)
解説:買取を行わない不動産屋は、売却依頼を受けた物件の買い手を探す必要があるため、購入意欲のある投資家に情報を流してくれる可能性が高いからです。
解答7:2. 取引の公平性が担保されないことがあるため、必ずしも得とは言えない。(P.60)
解説:媒介業者が間に入ることで、客観的な視点から取引の公平性や適正さが保たれるというメリットがあります。
解答8:3. 一オーナーレベルで管理の質を変えるのは難しいため、購入は見送るのが無難。(P.62)
解説:マンション全体の管理は管理組合の領域であり、一個人の力で改善するのは困難なため、管理の質が悪い物件は避けるべきだとされています。
解答9:3. 購入申込書を提出するとき(P.67, 76)
解説:ローン特約は重要な契約条件の一つなので、最初の意思表示である購入申し込みの段階で、その希望を明確に伝えておく必要があります。
解答10:2. 道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退(セットバック)させる。(P.70)
解説:将来的に道路の幅員を4m確保するために、敷地の一部を道路として提供する必要があります。これをセットバックといいます。
解答11:3. 良好な関係を築くため、なるべく親しくなる。(P.52)
解説:著者は、馴れ合いになると気のゆるみからいい加減な対応をされる可能性があるため、むしろ「うるさい客」だと思わせるくらいの緊張感を保つべきだと述べています。
解答12:2. 入居者募集の窓口となる不動産屋さん(媒介契約)(P.130)
解説:窓口を一本化(専任媒介契約)することで、対応の煩雑さを避け、責任の所在を明確にできるというメリットがあります。
解答13:2. 顧客が多い不動産屋では、優先順位の低い客には良い情報が回ってこないということ。(P.51)
解説:年収や自己資金などで顧客の優先順位が決められ、下流の客(優先順位の低い客)には上流の客が選ばなかった物件しか回ってこない状況を例えています。
解答14:2. 防火地域内にある耐火建築物の場合(P.72)
解説:防火地域内にある耐火建築物や、特定行政庁が指定する角地にある建築物は、建ぺい率が10%緩和されます。
解答15:3. 既存不適格建築物とは、建築当時は適法だったが、その後の法改正で基準に適合しなくなった建物のことである。(P.72)
解説:一方、違法建築物は建てられた当初から法律に違反している建物を指します。この二つは明確に区別されます。
解答16:① 成功(P.53)
解説:仲介手数料は、売買契約や賃貸借契約を成立させたことに対する成功報酬です。
解答17:宅建士(宅地建物取引士)(P.54)
解説:不動産屋を開業するには専任の宅建士が必要なため、まずはこの国家資格を取得することが最難関であり、最初のステップとなります。
解答18:リフォーム(P.48)
解説:建物の建て替えはできませんが、内装や外装を修繕・改装するリフォームは可能です。
解答19:市街化調整(P.74)
解説:市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則として新たな建築が制限されています。
解答20:事前審査(P.42)
解説:本審査の前に、融資が受けられそうかどうかの見込みを立てるための審査です。これにより、契約後の手続きをスムーズに進めることができます。
解説を読んでみても、よくわからない問題については、あらためて書籍の該当箇所を確認してみて下さい。