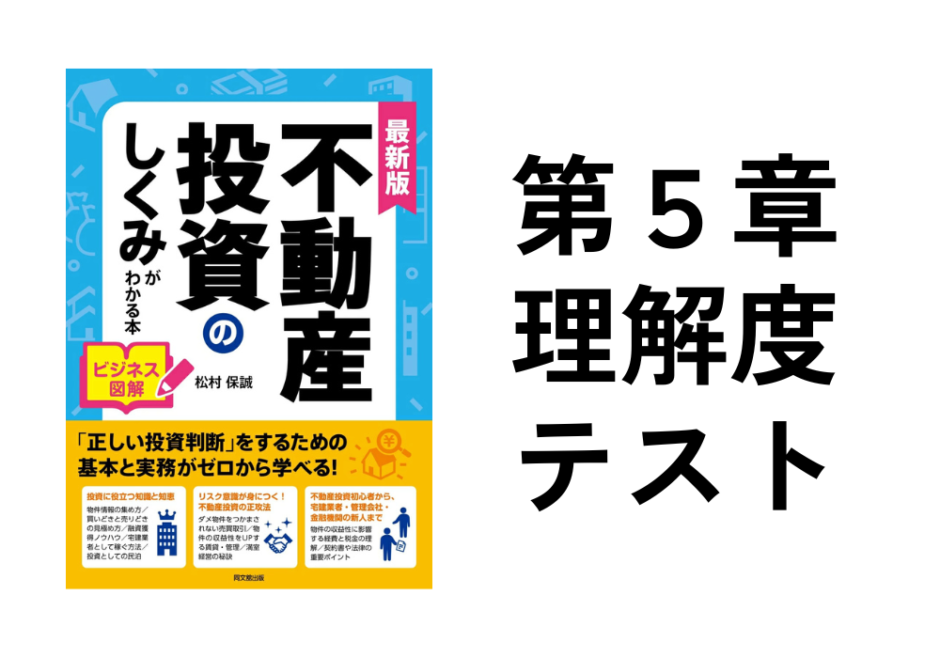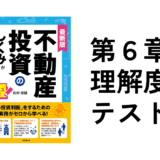不動産投資のしくみがわかる本、第5章の理解度テストアプリです。
完全マスターを目指して、繰り返しチャレンジしてみて下さい。
不動産投資 第5章
学習クイズアプリ
『ビジネス図解 不動産投資のしくみがわかる本』第5章の理解度をテストします。
挑戦するレベルを選択してください。
クイズ終了!
あなたのスコアは…
最終確認テスト
アプリで取り上げられている全問題を掲載しておきます。
最終確認テストにはこちらをご利用ください。
【初級編】(全20問)
物件運営に関する基本的な知識や流れの理解度をチェックします。
問1. 著者が挙げる、良い管理会社を選ぶための3つの基準に含まれないものはどれですか?
- 物件のそばに店舗があるか
- 管理手数料が最も安いか
- 管理物件数が多いか
問2. 管理会社に委託できる3つの主な業務として、本書で挙げられているものは、契約管理業務、清掃業務とあと一つは何ですか?
- 設備管理業務
- 税務申告業務
- 入居者の送迎業務
問3. 自分で物件を管理する場合、入居者募集の窓口となる不動産屋さん(媒介契約)は、どのようにすべきだと述べられていますか?
- なるべく多くの不動産屋さんに個別にお願いする
- 必ず1社に固定する(専任媒介契約)
- 自分で直接入居者を探す
問4. 空室期間を短縮するために、賃貸営業マンに優先的に物件を案内してもらう方法として、本書で推奨されていることは何ですか?
- 広告料を引き上げる
- 営業マンに個人的なプレゼントを渡す
- 家賃を相場より大幅に高く設定する
問5. 空室期間が長引いても安易に家賃を下げるべきでない理由として、本書で挙げられていることは何ですか?
- 将来的な売却価格が下がることにもつながるから
- 法律で家賃の値下げが禁止されているから
- 既存の入居者が家賃を上げてほしいと要求してくるから
問6. 追加投資なしで物件の収益性を上げるためのアイデアとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- 全ての部屋をリノベーションする
- ペットの室内飼育を可能にする
- 最寄り駅までのシャトルバスを運行する
問7. 入居審査を行う主な目的は何ですか?
- なるべく高い家賃を払ってくれる人を見つけるため
- 賃料を滞納したり、トラブルを起こしたりする可能性が高い人を排除するため
- 申込者の家族構成を詳しく知るため
問8. 入居者が賃料を滞納した場合に、代わりに弁済してくれる会社のことを何といいますか?
- 家賃保証会社
- 信用金庫
- 管理組合
問9. 賃貸借契約書において、借主が通常の使用によって生じた損耗(例:家具の設置による床のへこみ)の修繕費用は、原則として誰が負担しますか?
- 貸主(大家)
- 借主(入居者)
- 貸主と借主で折半
問10. 貸主側から賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするために必要とされる、法律上の正当な理由のことを何といいますか?
- 特別事由
- 正当事由
- 優先事由
問11. 家賃滞納者に対して、いつ、誰から、どんな内容の郵便が送られたかを郵便局が証明してくれる制度を何といいますか?
- 特別送達
- 書留郵便
- 内容証明郵便
問12. 入居者が退去した後、次の入居者を募集するために最低限行わなければならないことは何ですか?
- ハウスクリーニング
- 壁紙の全面張り替え
- 間取りの変更
問13. 物件の魅力度を大幅にアップさせるために、間取りから変えるような大規模なリフォームのことを何といいますか?
- リフレッシュ
- リノベーション
- リコンストラクション
問14. (○か×か)管理会社の質は、物件の実質利回りにほとんど影響を与えない。
問15. (○か×か)自分で物件を管理する場合、家賃が少しでも遅れたらすぐに督促すべきである。
問16. (○か×か)入居審査において、申込者の人間性は審査項目に含まれない。
問17. (○か×か)借地借家法では、貸主よりも借主の権利が強く保護されている傾向にある。
問18. (○か×か)物件内で死亡事故があった場合、その事実を次の入居者に告知する必要は一切ない。
問19. (○か×か)リノベーションは、必ず費用以上の収益増が見込めるため、積極的に実施すべきである。
問20. (○か×か)家賃保証会社を利用すれば、連帯保証人は不要である。
【上級編】(全20問)
より専門的な知識や、著者の考え方に対する深い理解度をチェックします。
問1. 管理会社が物件のそばに店舗を持つことのメリットとして、著者が挙げている点は何ですか?
- 入居者満足度のアップとトラブルの最小化につながるから。
- 家主が気軽に立ち寄り、お茶を飲めるから。
- 近隣の物件の情報をいち早く入手できるから。
問2. 著者がコラムで、賃貸業者の営業マンの中でも特にその能力を活用すべきだと考えているのは、どちらの業務を主に行っている営業マンですか?
- 主に貸主側の媒介業務をしている営業マン
- 主に借主側の媒介業務をしている営業マン
- 貸主・借主双方の業務を均等に行っている営業マン
問3. 自分で管理する場合に媒介契約を1社に固定(専任媒介契約)すると、どのような副次的なメリットが期待できると述べられていますか?
- 仲介手数料が半額になる。
- その不動産屋さんが、入居者からのクレーム対応など管理業務の一部を無償で代行してくれることがある。
- 広告料を支払う必要がなくなる。
問4. 賃貸営業マンに案内してもらいやすくするために、現地にキーボックスを設置するなどの工夫をすることは、どのような効果を狙ったものですか?
- 営業マンの物件への案内の手間を減らし、効率を上げるため。
- 鍵の紛失リスクを減らすため。
- 家主が不在でも内覧できるようにするため。
問5. 家賃を下げずに入居者を募集する方法として、本書で挙げられている「フリーレント」とは具体的にどのような手法ですか?
- 入居期間中、ずっと家賃が無料になる。
- 入居当初の数ヶ月間、家賃を無料にする。
- 礼金を無料にする。
問6. 家賃保証会社を選ぶ際のポイントとして、本書で挙げられている保証範囲の最低ラインはどれですか?
- 月額賃料の6ヶ月分
- 月額賃料の12ヶ月分と訴訟費用
- 月額賃料の24ヶ月分と原状回復費、残置物撤去費用、訴訟費用
問7. 賃貸住宅標準契約書において、借主からの解約申し入れは何日前までに行う必要があるとされていますか?
- 10日前
- 30日前
- 60日前
問8. 借地借家法において、貸主が契約の更新をしない旨の通知をしなければならない期間はいつからいつまでですか?
- 期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前まで
- 期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前まで
- 期間満了の1年前から6ヶ月前まで
問9. 家賃滞納者との話し合いで、口頭だけでなく「覚書」などの書面で確約をもらうことの主な目的は何ですか?
- 後日のトラブルを防ぎ、約束の内容を明確にするため。
- 滞納者に心理的なプレッシャーを与えるため。
- 裁判を起こす際の印紙代を安くするため。
問10. 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、一回の期日で審理が終わり即日判決が出る特別な訴訟制度を何といいますか?
- 支払督促
- 少額訴訟
- 民事調停
問11. 物件内で死亡事故があった場合、相続人に対して家主が求めるべき最低限の対応は何ですか?
- 損害賠償全額の支払い
- 残置物の撤去と敷金の権利放棄
- 今後一切関わらないという念書の提出
問12. リノベーションを実施するかどうかの判断の第二段階として、著者が検討すべきとしている計算式はどれですか?
- 増加収益 > 投下資本
- 増加収益 < 投下資本
- 増加収益 = 投下資本
問13. 著者が、家賃滞納の対応について管理会社に委託している場合でも家主が注意すべき点として挙げていることは何ですか?
- 管理会社にすべて任せきりにせず、対応がまずい担当者には具体的に指示を出すこと。
- 家主が直接、滞納者と交渉すること。
- 管理会社の手数料を値切ること。
問14. 借主の故意や過失による損耗(例:喫煙によるクロスの黄ばみ)の修繕費用は、誰が負担すべきですか?
- 貸主(大家)
- 借主(入居者)
- 全額を家賃保証会社が負担する
問15. 借地借家法にある「造作買取請求権」を事前に行使できないようにするためには、どのような対策が有効ですか?
- 口頭で借主の同意を得ておく。
- 賃貸借契約書に、この権利を排除する特約を設けておく。
- そもそも借主による造作の付加を一切同意しない。
問16. (穴埋め)家賃滞納の対処法として、話し合いで解決できない場合は法的手段に訴えることになりますが、滞納家賃の回収だけでなく、賃借人を退去させたい場合には( )訴訟を最初から行うべきである。
問17. (穴埋め)管理会社選びの3つの基準を満たす会社が複数ある場合、さらに絞り込む基準として、自社での直接的な入居者募集能力、いわゆる( )能力を挙げている。
問18. (穴埋め)入居審査の基準として、賃料の12ヶ月分が年収の( )以内に収まっているかどうかが、よく言われる目安である。
問19. (穴埋め)貸主と借主が合意していなくても、一定の条件を満たすと自動的に契約が更新されることを( )更新という。
問20. (穴埋め)著者は自身の経験から、物件内での事故の告知について、「確実にトラブルを避けたいのなら、借主が( )かもしれないことはなるべく伝えておくほうがいい」とアドバイスしている。
解答と解説
【初級編】
解答1:2. 管理手数料が最も安いか(P.126)
解説:手数料の安さだけで選ぶと、管理の質が低く、かえって収益性が悪化する可能性があります。著者は「物件のそばにあるか」「修繕スタッフがいるか」「管理物件数が多いか」を基準に挙げています。
解答2:1. 設備管理業務(P.128)
解説:契約管理(家賃徴収など)、清掃、設備管理(エレベーター点検など)が管理会社に委託できる3つの主な業務です。
解答3:2. 必ず1社に固定する(専任媒介契約)(P.130)
解説:窓口を一本化することで、対応が煩雑になるのを防ぎ、入居者募集に対する不動産屋さんの責任感を高めることができます。
解答4:1. 広告料を引き上げる(P.134)
解説:賃貸営業マンの給与は歩合給の割合が大きいため、成功報酬である広告料が高い物件を優先的に紹介する傾向があります。
解答5:1. 将来的な売却価格が下がることにもつながるから(P.136)
解説:家賃の値下げは表面利回りの低下を意味し、収益物件としての評価額(売却価格)も下がってしまいます。
解答6:2. ペットの室内飼育を可能にする(P.138)
解説:ペット可物件は供給が少ないため、それだけで競合物件との差別化になり、賃料アップや空室期間の短縮が期待できます。
解答7:2. 賃料を滞納したり、トラブルを起こしたりする可能性が高い人を排除するため(P.142)
解説:安定した賃貸経営のためには、入居後のトラブルを未然に防ぐことが非常に重要です。
解答8:1. 家賃保証会社(P.144)
解説:入居者が保証料を支払うことで、滞納時に家賃を立て替えてくれるサービスです。家主にとっては家賃滞納リスクを軽減できるメリットがあります。
解答9:1. 貸主(大家)(P.146)
解説:経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は、家賃に含まれるものと考えられており、その修繕費用は貸主が負担するのが原則です。
解答10:2. 正当事由(P.148)
解説:貸主側の都合だけで一方的に契約を終了させることは難しく、「貸主がその建物を自ら使用する必要性が非常に高い」など、客観的に見て正当と認められる理由が必要です。
解答11:3. 内容証明郵便(P.154)
解説:法的な強制力はありませんが、相手に「法的手続きを準備している」という強い意志を伝え、支払いを促す心理的効果があります。
解答12:1. ハウスクリーニング(P.158)
解説:前の入居者の生活感が残っていると、次の入居希望者に良い印象を与えません。プロによる専門的な清掃は必須です。
解答13:2. リノベーション(P.160)
解説:単なる原状回復(リフォーム)にとどまらず、新たな付加価値を創造することで、物件の競争力を高めることを目的とします。
解答14:×(P.127)
解説:著者は「管理会社の質で実質利回りが1%単位で変わる」と述べており、運営のパートナー選びが収益性を大きく左右すると考えています。
解答15:○(P.132)
解説:家賃滞納は放置すればするほど回収が困難になるため、「うるさい家主」と思われるくらい迅速に対応することが重要です。
解答16:×(P.142)
解説:入居希望者と面談した担当者の意見を聞くなどして、申込者の人柄や信頼性も判断する必要があります。
解答17:○(P.148)
解説:借地借家法は、居住の安定という観点から、借主(入居者)の権利を保護する規定が多くなっています。
解答18:×(P.190)
解説:判例上も明確な基準はありませんが、後のトラブルを避けるため、事故の内容によっては告知する義務が生じると考えられています。
解答19:×(P.160)
解説:費用倒れになるケースも多いため、その地域の需要や、費用対効果(投下資本以上に収益が増加するか)を慎重に検討する必要があります。
解答20:×(P.143)
解説:家賃保証会社は金銭的なトラブルにしか対応しないため、騒音などのマナートラブルに対応してもらうためにも、連帯保証人を立ててもらう方が望ましいです。
【上級編】
解答1:1. 入居者満足度のアップとトラブルの最小化につながるから。(P.126)
解説:トラブル発生時に迅速に対応できるため、問題が大きくなるのを防ぎ、入居者の満足度向上(→長期入居)にもつながります。
解答2:2. 主に借主側の媒介業務をしている営業マン(P.162)
解説:日々多くの入居希望者を様々な物件に案内しているため、お客さんの視点から見た物件の魅力や相場観を最も正確に把握しているからです。
解答3:2. その不動産屋さんが、入居者からのクレーム対応など管理業務の一部を無償で代行してくれることがある。(P.130)
解説:専任で任されることで責任感が生まれ、貸主との関係を良好に保つために、契約範囲外の業務でもサービスで対応してくれることが期待できます。
解答4:1. 営業マンの物件への案内の手間を減らし、効率を上げるため。(P.134)
解説:忙しい営業マンは、鍵の受け渡しなどで手間がかかる物件より、案内しやすい物件を優先する傾向があるため、案内数を増やす効果があります。
解答5:2. 入居当初の数ヶ月間、家賃を無料にする。(P.136)
解説:入居者の初期費用負担を大幅に軽減できるため、家賃を下げなくても入居希望者を引きつける強力なインセンティブになります。
解答6:3. 月額賃料の24ヶ月分と原状回復費、残置物撤去費用、訴訟費用(P.144)
解説:万が一、家賃滞納から明け渡し訴訟に至った場合でも、経済的損害を最小限に抑えられるよう、保証範囲が広い会社を選ぶべきだとされています。
解答7:2. 30日前(P.146)
解説:借主は30日前に申し入れることで契約を解約できます。また、30日分の家賃を支払えば即時解約も可能です。
解答8:3. 期間満了の1年前から6ヶ月前まで(P.148)
解説:この期間内に更新しない旨の通知をしないと、契約は自動的に更新(法定更新)されてしまいます。
解答9:1. 後日のトラブルを防ぎ、約束の内容を明確にするため。(P.150)
解説:「言った・言わない」の争いを避け、万が一家賃の支払いがなかった場合に、退去交渉などを進める上での証拠となります。
解答10:2. 少額訴訟(P.154)
解説:通常の訴訟に比べて手続きが迅速かつ簡便で、費用も安く済むメリットがあります。
解答11:2. 残置物の撤去と敷金の権利放棄(P.156)
解説:高圧的な態度で損害賠償を請求すると、相続人に相続放棄をされてしまい、最低限の対応すらしてもらえなくなるリスクがあります。
解答12:1. 増加収益 > 投下資本(P.160)
解説:リノベーションにかけた費用(投下資本)以上に、家賃アップや売却価格上昇による収益の増加が見込めるかどうかをシミュレーションし、投資判断を行う必要があります。
解答13:1. 管理会社にすべて任せきりにせず、対応がまずい担当者には具体的に指示を出すこと。(P.152)
解説:管理会社に委託していても、最終的な責任は家主にあります。状況を把握し、必要に応じて具体的な指示を出すことが重要です。
解答14:2. 借主(入居者)(P.184)
解説:借主には「善管注意義務」があり、故意や不注意によって生じさせた損耗については、原状回復費用を負担する義務があります。
解答15:2. 賃貸借契約書に、この権利を排除する特約を設けておく。(P.149)
解説:造作買取請求権は、当事者間の特約で排除することが認められています(任意規定)。トラブルを避けるため、契約書に明記しておくのが一般的です。
解答16:明渡し請求(P.154)
解説:支払督促や少額訴訟は金銭の請求が目的であり、退去を強制することはできません。退去を求める場合は、通常の訴訟(建物明渡請求訴訟)が必要です。
解答17:客付け(P.127)
解説:「客付け」とは、入居者を見つけてくる能力のことです。管理能力だけでなく、空室を埋める力があるかも重要な選定基準となります。
解答18:3割(P.142)
解説:例えば年収300万円の人であれば、年間の家賃負担が90万円(月7.5万円)以内に収まるかどうかが一つの審査基準になります。
解答19:法定(P.148)
解説:貸主が更新拒絶の通知を怠ったり、期間満了後も借主が住み続けているのに異議を述べなかったりした場合に、法律の規定によって契約が更新されます。
解答20:気になる(P.190)
解説:法律上の告知義務の有無だけでなく、入居者が後から知ってどう思うか、という視点で判断し、トラブルの芽を未然に摘んでおくことが賢明だという考えです。
解説を読んでみても、よくわからない問題については、あらためて書籍の該当箇所を確認してみて下さい。