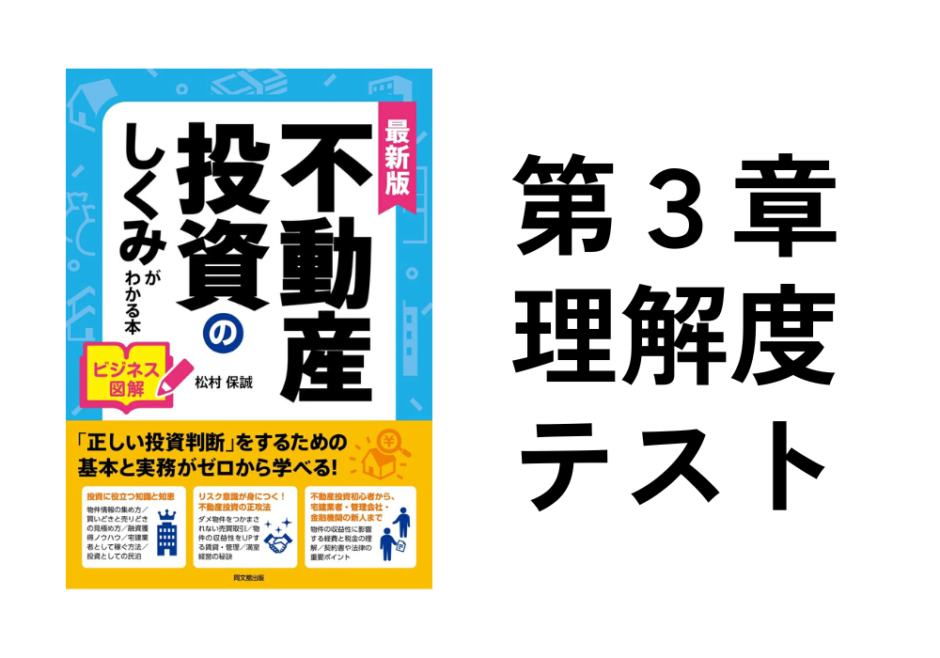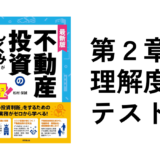不動産投資のしくみがわかる本、第3章の理解度テストアプリです。
完全マスターを目指して、繰り返しチャレンジしてみて下さい。
不動産投資 第3章
学習クイズアプリ
『ビジネス図解 不動産投資のしくみがわかる本』第3章の理解度をテストします。
挑戦するレベルを選択してください。
クイズ終了!
あなたのスコアは…
最終確認テスト
アプリで取り上げられている全問題を掲載しておきます。
最終確認テストにはこちらをご利用ください。
【初級編】(全20問)
物件種別の特徴や基本的な用語の理解度をチェックします。
問1. 一棟ものマンション・アパートのメリットとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- 価格が安い
- 管理が楽である
- 空室リスクをコントロールしやすい
問2. 区分所有マンションのデメリットとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- 運営の自由度が低い
- 利回りが高い
- 売却しにくい
問3. 古い戸建物件のメリットとして、適切なものはどれですか?
- 管理に手間がかからない
- ほぼ土地価格で購入できるため、利回りが高くなりやすい
- 金融機関からの融資が利用しやすい
問4. 店舗や事務所などの事業用物件のデメリットとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- 利回りが低い
- 賃料の振れ幅が小さい
- 居住用物件に比べて空室リスクが高い
問5. 新築物件のメリットとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- 利回りが高い
- 長期運用が可能である
- 購入価格が安い
問6. 不動産の収益性を判断する指標の一つ「表面利回り」の計算式として正しいものはどれですか?
- 年間賃料 ÷ 物件価格 × 100
- (年間賃料 – 年間経費) ÷ 物件価格 × 100
- 物件価格 ÷ 年間賃料 × 100
問7. 年間賃料から年間の必要経費を差し引いて計算する、より正確な収益性の判断基準を何といいますか?
- 満室時想定利回り
- 表面利回り
- 実質利回り
問8. 収益用一棟マンションなどで、各部屋の入居者や賃貸条件を一覧にした表のことを何といいますか?
- レントゲン
- レントロール
- レンタルリスト
問9. 自分が住んでいる地域の近辺にある不動産に投資する「近場の不動産投資」のメリットは何ですか?
- 利回りが非常に高い
- 物件の選択肢が無限に広がる
- 地域の特性がわかり、投資判断がしやすい
問10. 投資物件の現在の運営状況を調べる際に、必ず確認すべき事項として本書で挙げられているものはどれですか?
- 入居者の趣味
- 家賃滞納者の有無
- 前の所有者の氏名
問11. 不動産の価格を判断する方法として、本書で紹介されているものはどれですか?
- 占い師に相談する方法
- 同じような物件の取引事例から判断する方法
- じゃんけんで決める方法
問12. 入居者募集を容易にするため、入居当初の1ヶ月〜数ヶ月間の賃料を無料にすることを何といいますか?
- フリーレント
- サービス期間
- お試し入居
問13. 一棟ものマンション・アパートのデメリットとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- リスクが小さい
- 価格が高い
- 運営の自由度が低い
問14. 区分所有マンションのメリットとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- 価格が高く、リスクが大きい
- 管理が大変である
- 価格が安く、リスクが小さい
問15. 店舗や事務所などの事業用物件は、居住用物件に比べてどのような傾向がありますか?
- 利回りが高い傾向にある
- 景気の影響を受けにくい
- 融資が利用しやすい
問16. (○か×か)不動産投資の判断は、物件資料に掲載されている表面利回りだけを見て行えば十分である。
問17. (○か×か)遠方の不動産への投資は、近場の不動産への投資に比べて、ハイリスク・ハイリターンになりやすい。
問18. (○か×か)新築物件は中古物件に比べて賃料をかなり高く設定できるため、利回りも非常に高くなる。
問19. (○か×か)家賃滞納者がいる物件でも、大幅な値引き交渉の材料と捉え、積極的に購入を検討すべきである。
問20. (○か×か)戸建物件は、一棟ものマンションに比べて管理に手間がかからないのが一般的である。
【上級編】(全20問)
より専門的な知識や、著者の考え方に対する深い理解度をチェックします。
問1. 著者が指摘する、一棟ものマンション・アパートが持つ特有のリスクとは何ですか?
- 入居者が増える分、管理が大変になること。
- 災害発生時などには、リスクにもレバレッジがかかること。
- 運営の自由度が高すぎること。
問2. 区分所有マンションでリスク分散を図る方法として、本書で紹介されているのはどのようなアプローチですか?
- 同じマンションの部屋を複数購入する。
- 地域や間取りタイプの違うマンションを複数戸購入する。
- 管理費や修繕積立金が高い物件を選ぶ。
問3. 著者の価値観別投資対象の分類で、「ある程度の利回りはほしいが、あまり高いリスクはとりたくない」という人に最も適しているとされる物件種別は何ですか?
- 一棟ものマンション・アパート
- 区分所有マンション
- 戸建
問4. 事業用物件と居住用物件の賃料の動きについて、正しい説明はどれですか?
- 居住用物件は景気による賃料の振れ幅が大きい。
- 事業用物件は景気が悪くなると賃料が下がりやすく、良くなると上がりやすい。
- どちらも景気による賃料の変動はほとんどない。
問5. 新築物件が持つ税務上のメリットとして、著者が挙げている点は何ですか?
- 固定資産税が永久に免除される。
- 建物減価償却費が大きいため、損益通算による節税効果が期待できる。
- 売却時の譲渡所得税がかからない。
問6. 不動産価格の判断方法の一つである「DCF法」が、収益を評価する際に用いる重要な概念は何ですか?
- 収益の将来価値
- 収益の現在価値
- 収益の平均値
問7. 表面利回りが、その物件の本来の収益性よりも高く見えてしまうケースとして、本書で挙げられているものはどれですか?
- 現在の入居者が長期間住んでいる。
- フリーレント期間を導入している。
- 敷金・礼金が高い。
問8. レントロールを読み解く際、関西の収益物件取引で特に注意が必要だとされる敷金の取り扱い方法は何ですか?
- 敷金全額没収方式
- 敷金倍返し方式
- 敷金債務持ち回り方式
問9. レントロールを見て、入居者が特定の大学の学生に偏っている場合に想定すべきリスクは何ですか?
- 学生のマナーが悪化するリスク。
- 大学が移転した場合に一斉退去されるリスク。
- 家賃の支払いが遅れがちになるリスク。
問10. 単身者向け1K物件の競合状況を調査する際、なぜワンルームや1DKの物件状況も確認すべきだと著者は述べていますか?
- 将来的に間取りを変更する可能性があるから。
- 同じ単身者がターゲットであるという意味で、競合物件といえるから。
- 法律で調査が義務付けられているから。
問11. 遠方にある地方の不動産を購入する場合に、著者が「事前にしっかりと検討する必要がある」と特に強調していることは何ですか?
- その地域の歴史や文化
- その不動産に対する将来的な需要の変化
- 現地までの交通費
問12. 投資物件の運営状況を調べる際、現在の入居者の平均入居期間が長い場合に注意すべきことは何ですか?
- 入居者が物件を私物化している可能性があること。
- 長期入居者が立て続けに退去すると、賃料水準が下がり、原状回復費がかさむこと。
- 次の入居者が見つかりにくいこと。
問13. 物件資料の表面利回りが実態を反映していない可能性があるため、より正確な賃料相場を把握する方法として著者が推奨しているのは何ですか?
- インターネットの口コミサイトで調べる。
- 物件の最寄り駅にある賃貸業者の営業マンに意見を求める。
- 自分で周辺物件の家賃を平均して算出する。
問14. 利回りが低い物件に対する著者の考え方として、最も近いものはどれですか?
- 利回りが低い物件は、どのような理由があってもダメ物件である。
- 利回りが低くても、大きな売却益(キャピタルゲイン)が見込めるなら投資対象になりうる。
- 利回りが低い物件は、初心者向けの安全な物件である。
問15. 著者がコラムで、2025年以降の不動産市場に影響を与える要因として挙げているものは、円安、少子高齢化と、あと一つは何ですか?
- AIの急速な発展
- アメリカの保護主義的な政策
- 新型ウイルスのパンデミック
問16. (穴埋め)不動産価格を原価から判断する方法では、その不動産をゼロから作る費用から建物の( )分を差し引いて価格を判断する。
問17. (穴埋め)レントロールとは、収益用一棟マンションなどで各居室ごとの借主の名前や( )等を一覧にしたもののことである。
問18. (穴埋め)築浅物件は、( )物件が増えた場合に、新規入居者の募集に際して賃料を大きく引き下げざるを得なくなることがある。
問19. (穴埋め)関西では収益物件の取引において、売主から買主に敷金分の金銭の引き継ぎを行わないにもかかわらず、返還債務だけが引き継がれる( )方式がとられることが多い。
問20. (穴埋め)著者は、投資対象としての物件の種別間に優劣はなく、自分の( )に合ったものを選択することが大切だと述べている。
解答と解説
【初級編】
解答1:3. 空室リスクをコントロールしやすい(P.80)
解説:部屋数が多いため、1つや2つの空室が出ても他の部屋からの家賃収入でカバーでき、収入が安定しやすいです。
解答2:1. 運営の自由度が低い(P.82)
解説:マンション全体のルール(管理規約)に従う必要があり、ペット飼育や事務所利用などを所有者が勝手に決めることはできません。
解答3:2. ほぼ土地価格で購入できるため、利回りが高くなりやすい(P.84)
解説:古い戸建は建物価値が低いため安く購入でき、その割に家賃は取れるため、結果的に利回りが高くなる傾向があります。
解答4:3. 居住用物件に比べて空室リスクが高い(P.86)
解説:事業用物件は景気の影響を受けやすく、ビジネスが不調になるとすぐに退去につながるため、空室になるリスクが高いです。
解答5:2. 長期運用が可能である(P.88)
解説:建物が新しいため、耐用年数が長く残っており、長期間にわたって安定した運用が期待できます。
解答6:1. 年間賃料 ÷ 物件価格 × 100(P.92)
解説:これは最も基本的な利回りの計算方法で、経費を考慮しない大まかな収益性を示します。
解答7:3. 実質利回り(P.92)
解説:固定資産税や管理費などの経費を考慮するため、表面利回りよりも現実に近い収益性を判断できます。
解答8:2. レントロール(P.96)
解説:一棟ものの収益物件を評価する上で非常に重要な資料で、現在の賃貸状況や将来の収益性を予測する手がかりとなります。
解答9:3. 地域の特性がわかり、投資判断がしやすい(P.100)
解説:自分がよく知っているエリアであれば、賃貸需要の高い場所や人気のなさそうな場所などが直感的にわかり、判断を誤るリスクを減らせます。
解答10:2. 家賃滞納者の有無(P.102)
解説:家賃滞納者がいると、購入後にその回収や立ち退き交渉で大きな手間と費用がかかる可能性があるため、事前の確認が不可欠です。
解答11:2. 同じような物件の取引事例から判断する方法(P.90)
解説:周辺の似たような物件がいくらで取引されているかを調べることで、検討中の物件価格が妥当かどうかを判断します。
解答12:1. フリーレント(P.95)
解説:入居者の初期費用負担を軽くすることで、入居のハードルを下げ、空室期間を短縮する効果が期待できます。
解答13:2. 価格が高い(P.80)
解説:建物一棟を丸ごと購入するため、区分所有マンションや戸建に比べて購入価格は格段に高くなります。
解答14:3. 価格が安く、リスクが小さい(P.82)
解説:一室単位で購入できるため投資額を抑えられ、万が一失敗したときのリスクも比較的小さく済みます。
解答15:1. 利回りが高い傾向にある(P.86)
解説:事業用物件はリスクが高い分、居住用物件よりも高い賃料を設定できることが多く、利回りも高くなる傾向があります。
解答16:×(P.92)
解説:表面利回りは経費を考慮していないため、これだけで判断すると実際の収支がマイナスになる危険性があります。必ず実質利回りや他の要素も検討すべきです。
解答17:○(P.101)
解説:遠方の物件は情報収集や管理が難しくなるなどのリスクがある一方、都心部より高い利回りが期待できるため、ハイリスク・ハイリターンな投資とされています。
解答18:×(P.88)
解説:新築物件は購入価格が高い割に、賃料は中古と比べてそこまで高く設定できないため、利回りは非常に低くなるのが一般的です。
解答19:×(P.103)
解説:著者は、家賃滞納者の退去を実現するのは簡単ではないため、原則として売主の責任で退去してもらってから取引に入るべきだと述べています。
解答20:×(P.84)
解説:古い戸建は故障個所が発生しやすく、特に空き家期間が長かった物件は管理に手間がかかる傾向があると指摘されています。
【上級編】
解答1:2. 災害発生時などには、リスクにもレバレッジがかかること。(P.80)
解説:投資対象が1つの建物に集中しているため、火災や地震などの災害が起きた場合、被害が全資産に及ぶという大きなリスクがあります。
解答2:2. 地域や間取りタイプの違うマンションを複数戸購入する。(P.82)
解説:関東と関西、ワンルームとファミリータイプなど、異なる特性の物件を複数持つことで、特定の地域や需要層の変化による影響を和らげることができます。
解答3:3. 戸建(P.85)
解説:著者は、戸建は一棟ものほどリスクが高くなく、区分所有ほど利回りが低くない、バランスの取れた選択肢として位置づけています。
解答4:2. 事業用物件は景気が悪くなると賃料が下がりやすく、良くなると上がりやすい。(P.87)
解説:事業用物件の賃貸需要は企業の業績など景気動向に大きく左右されるため、賃料の変動幅も居住用物件より大きくなります。
解答5:2. 建物減価償却費が大きいため、損益通算による節税効果が期待できる。(P.89)
解説:新築物件は取得価額に占める建物割合が高く、減価償却費を大きく計上できます。これにより不動産所得が赤字になれば、給与所得などと損益通算して所得税の還付を受けられる可能性があります。
解答6:2. 収益の現在価値(P.90)
解説:DCF法(Discounted Cash Flow法)は、将来得られるであろう収益(キャッシュフロー)を、現在の価値に割り引いて合計し、物件の価値を算出する方法です。
解答7:2. フリーレント期間を導入している。(P.94-95)
解説:フリーレントを導入する場合、その分を見越して毎月の賃料を高めに設定することがあります。そのため、レントロール上の賃料から計算した表面利回りは、実態より高く見えることがあります。
解答8:3. 敷金債務持ち回り方式(P.97)
解説:売主が預かった敷金を買主に引き継がないのに、借主への返還義務だけは買主が負うという、買主にとって不利な取引慣行です。購入金額が実質的に上がることになるため注意が必要です。
解答9:2. 大学が移転した場合に一斉退去されるリスク。(P.96)
解説:入居者の属性に偏りがあると、その属性に影響を与える出来事(企業の事業所移転や大学のキャンパス移転など)が起きた際に、空室が一気に増えるリスクがあります。
解答10:2. 同じ単身者がターゲットであるという意味で、競合物件といえるから。(P.98)
解説:単身者は1Kだけでなく、広さや家賃によってはワンルームや1DKも検討します。そのため、直接的な競合だけでなく、代替となりうる物件の状況も把握することが重要です。
解答11:2. その不動産に対する将来的な需要の変化(P.101)
解説:地方の物件は、人口減少などにより将来的に需要が大きく低下し、「売りたくても売れない」状態になるリスクがあります。利回りの高さだけでなく、長期的な需要を見極めることが重要です。
解答12:2. 長期入居者が立て続けに退去すると、賃料水準が下がり、原状回復費がかさむこと。(P.102)
解説:長く住んでいた入居者が退去すると、次の募集では現在の相場に合わせて賃料を下げざるを得ず、また、室内の損耗も激しいため原状回復費用も高額になりがちです。
解答13:2. 物件の最寄り駅にある賃貸業者の営業マンに意見を求める。(P.94)
解説:地域の賃料相場を最も正確に把握しているのは、日々入居希望者を案内している現場の営業マンであるため、彼らの意見を聞くことが最も有効だとされています。
解答14:2. 利回りが低くても、大きな売却益(キャピタルゲイン)が見込めるなら投資対象になりうる。(P.93)
解説:利回りはあくまで投資判断基準の一つにすぎません。将来的な値上がりが期待できるなど、トータルで利益が見込めるのであれば、投資する価値はあるという考え方です。
解答15:2. アメリカの保護主義的な政策(P.104)
解説:トランプ政権の政策を例に挙げ、アメリカの政策が世界経済に与える影響は、日本の不動産価格の下落要因になりうると予測しています。
解答16:減価償却(P.90)
解説:原価法では、土地価格と、再調達価格から経年による価値の減少(減価償却)を差し引いた建物価格を合算して、不動産価格を判断します。
解答17:賃貸契約の条件(P.96)
解説:レントロールには、入居者名だけでなく、賃料、共益費、契約日、敷金・礼金の額など、各部屋の賃貸契約に関する詳細な条件が記載されています。
解答18:新築(P.98)
解説:周辺に魅力的な新築物件が供給されると、築浅物件は見劣りしてしまい、入居者を確保するために賃料の引き下げを余儀なくされることがあります。
解答19:敷金債務持ち回り(P.97)
解説:買主は敷金を受け取らないまま返還義務を負うため、その分の金額を実質的な購入費用として上乗せして利回りを計算する必要があります。
解答20:価値観(P.85)
解説:大きなリターンを狙いたいのか、リスクを抑えたいのかなど、投資家自身の価値観や目標に合った物件種別を選ぶことが、後悔のない投資につながります。
解説を読んでみても、よくわからない問題については、あらためて書籍の該当箇所を確認してみて下さい。